「働いて働いて働く」vs ワークライフバランス、あなたが誤解している本当の意味
- 吉田 薫

- 2025年10月15日
- 読了時間: 5分

〇政治家の発言で炎上したワークライフバランス、実は9割の人が勘違いしている
■「働け働け」発言の真の問題点
大物政治家の「働いて働いて働く」発言が物議を醸した。SNSでは賛否両論が飛び交い、「ワークライフバランス(WLB)を否定するのか」「いや、働きたい人の自由だ」と大炎上。
でも、ちょっと待ってほしい。
この議論、そもそもワークライフバランス(WLB)の意味を誤解していないだろうか?
〇ワークライフバランス=「働くな」じゃない!勘違いしている人、続出
まず、多くの人が持っているワークライフバランス(WLB)のイメージがこれだ。
• 「定時で帰ろう! 残業は悪!」
• 「頑張りすぎないことが大事」
• 「とにかく休もう、働きすぎはダメ」
• 「若い世代の新しい価値観」
正直に言おう。これ、全部間違っている。
WLBは「働くな」じゃない。「選べるようにしよう」なのだ。
〇本質は「システム設計」にあり
ここが最も重要なポイントだ。WLBを理解するには、2つの層で考える必要がある。
【第1層】会社や組織がやるべきこと
• フレックスやリモートワークなど、選択肢を用意する
• 「残業しないと評価されない」空気をなくす
• 子育て中でも、介護中でも働ける仕組み
• 休暇を取りやすい雰囲気づくり
これがWLBの本質。「働くな」じゃなくて「働き方を選べるようにする」制度設計のことだ。
【第2層】個人が決めること
• バリバリ働きたい人は働けばいい
• プライベート重視の人はそうすればいい
• 時期によって変えてもいい
• 誰かに強制されるものじゃない
つまり、「働きたい人」の意欲を奪うどころか、全員が自分らしく働ける環境を作るのがWLBなのだ。
〇歴史が証明する「放っておくとヤバい」理由
■産業革命で何が起きたか
ここで歴史の話をしよう。今の8時間労働制、どうやって生まれたか知っているだろうか?
「機械が発明されて、労働時間が短くなった」と思ったら大間違い。
18-19世紀の産業革命期、機械のおかげで生産性は爆上がりした。
でも労働時間は? なんと12-16時間に増えた。
なぜか。経営者は「生産性が上がったから労働時間を減らそう」なんて考えなかった。「もっと儲けよう」と考えたからだ。
■8時間労働は「闘争」の結果
8時間労働制は、労働者が必死に戦って勝ち取ったものだ。
• 1817年:ロバート・オーウェンが「8時間労働・8時間休息・8時間余暇」を提唱
• 1886年:アメリカで大規模ストライキ(これがメーデーの起源)
• 1919年:ILO(国際労働機関)が国際基準として採択
• 1947年:日本で労働基準法により法制化
つまり、技術が進歩しても、放っておけば労働者は搾取される。これが歴史の教訓だ。
■フォードが気づいた「経済の秘密」
1914年、ヘンリー・フォードは画期的なことをした。
労働時間を短くして、給料を上げたのだ。
なぜか? 従業員が自社の車を買えるようにするためだ。労働者を「消費者」に変えることで、経済が回り始めた。
労働時間短縮→余暇ができる→給料UP→モノが買える→経済成長
これが20世紀の大量消費社会を生んだ。制度設計が社会を変えたわけだ。
〇AI時代、またしても歴史は繰り返すのか
■週休3日、1日6時間労働の可能性
今、AIで生産性が爆上がりしている。産業革命の機械と同じだ。
週休3日制や1日6時間労働の実験も始まっている。いい流れだ。
でも、産業革命の教訓を忘れるな。放っておいたら、また一部の人だけが得をして、多くの人は長時間労働のまま、なんてことになりかねない。
■「バランス」から「統合」へ
これからのWLBは、もっと進化する必要がある。
20世紀型:仕事8時間 vs 生活16時間(キッチリ分ける)
21世紀型:仕事と生活を柔軟に組み合わせる(自分でデザイン)
たとえば:
• 20代はガッツリ働く→30代は育児と両立→40代は学び直し→50代は社会貢献
• 午前は集中作業、午後は家族時間、夜はまた少し仕事
• 副業・複業が当たり前
こういう「Work-Life Integration(統合)」こそが、AI時代のWLBだ。
■「働く」の定義も変わる
これまで「働く=会社で給料もらう」だった。
でも、これからは?
• 創造的な仕事に集中(ルーティンはAIに任せる)
• ボランティアや地域活動も「働く」
• 子育てや介護も「価値ある仕事」として認める
• ベーシックインカム的な議論も本格化

〇結局、何が正しいのか
■「働きたい人」vs「休みたい人」は不毛
冒頭の「働いて働いて働く」発言。これ自体は別に悪くない。
本人が働きたいなら、それは自由だ。
問題は「それを他の人にも強制する空気」だ。
影響力のある人が「働け働け」と言うと、「休みたい人」や「バランス重視の人」が悪者にされる。これがマズい。
■本当に必要なのは「選択の自由」
もう一度言おう。WLBの本質は「選べること」だ。
会社・組織がやるべきこと:
• 多様な働き方を選べる制度を作る
• 働き方の違いで差別しない
• 成果で評価する(時間じゃない)
個人が理解すべきこと:
• 自分のライフステージで選択を変えていい
• 他人の選択を尊重する
• 「働きたい」も「休みたい」も、どっちも正しい
■未来はどうなる?
8時間労働制が「消費社会」を生んだように、AI時代の新しい働き方は何を生むか。
• 創造社会:クリエイティブな仕事に人間が集中
• 学習社会:生涯学び続けることが当たり前に
• ケア社会:人と人のつながりが価値を持つ
そんな未来を実現するカギが、正しいWLBの理解なのだ。
〇まとめ:誤解を解いて、建設的な議論を
✓ WLBは「働くな」じゃなく「選べるようにしよう」
✓ 歴史が証明:放置すると搾取される
✓ AI時代こそ、適切な制度設計が必要
✓ 「働きたい人」も「休みたい人」も、どちらも尊重
✓ 未来は「Work-Life Integration」へ
誤解に基づいて「働け」vs「休め」で対立するのは時間のムダ。
本当の議論は「どうやって全員が自分らしく働ける社会を作るか」だ。
そのためには、WLBの正しい理解が不可欠。この記事が、建設的な対話のきっかけになれば幸いだ。

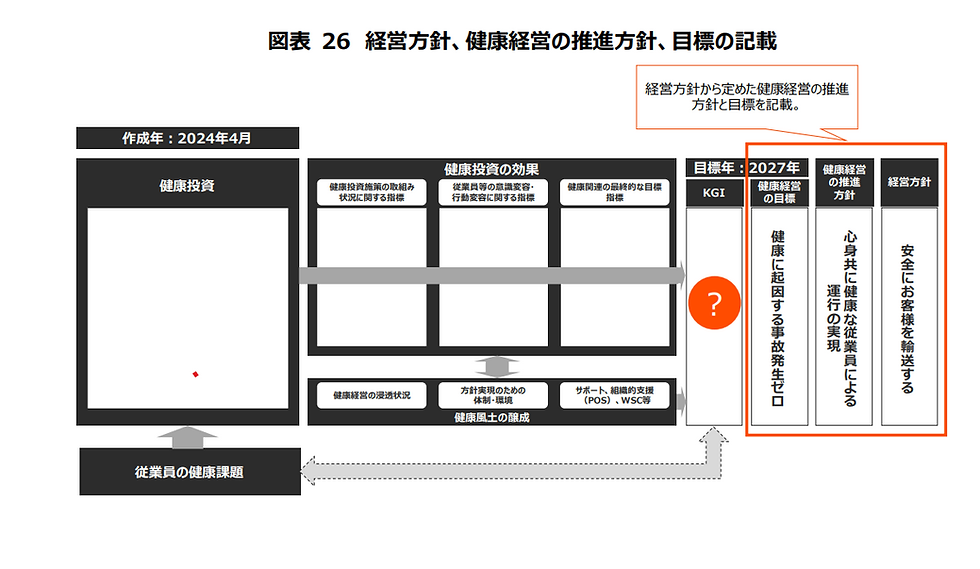


コメント